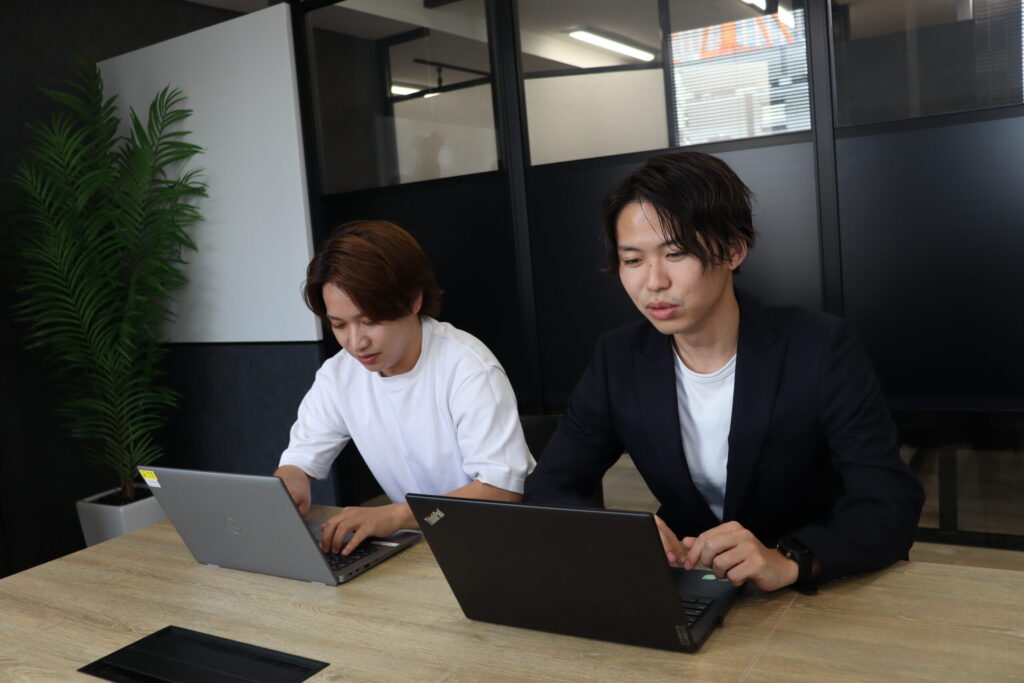プロが毎日使っている言葉を、できるだけやさしく・少し笑える形で解説します。
「職人さんが何言ってるか分からない…」
「見積書の単語が呪文に見える…」
そんな方に向けた、“読み物としてもおもしろい用語集”です。
あ行
アク止め
コンクリートやモルタルが持っている「アルカリ成分」が、
仕上げの塗料に悪さをしないようにするための“ストッパー役”の下塗り材。
最近のシーラーや外壁用上塗り材には、だいたいこのアク止め機能が含まれています。
つまり、見えないところでちゃんと働いている“縁の下の力持ち”です。
アクリル酸
刺激臭のある無色の液体で、アクリル樹脂などの原料。
聞くだけで理科の授業を思い出す名前ですが、
これがないとアクリル樹脂も塗料も始まりません。
アクリル樹脂
アクリルプラスチックやアセトン、苛性ソーダなどを組み合わせて作られる樹脂。
自動車・飛行機・建物など、かなり幅広く使われている“便利屋ポジション”です。
アクリル塗料
アクリル酸(またはメタクリル酸)の仲間を固めて作られた塗料。
透明感と光沢があり、見た目はかなり優秀ですが、
耐久年数はおおむね5〜7年ほどと短め。
今の外壁・屋根の主役は「ウレタン」「シリコン」などで、
アクリルは“かつてのエース、今は控えめなベテラン”という立ち位置です。
上げ裏(あげうら)
軒先など、下から見上げたときに見える“天井部分”。
軒裏とも呼びます。
庇の上げ裏は「庇裏」、階段の上げ裏は「段裏」と呼び分けたりします。
塗るのが地味に大変ですが、きれいだと家全体の印象がグッと上がります。
足場
外壁塗装のスタートとゴールを飾る脇役にして主役級の存在。
- 最初に組み立てる
- 作業中の安全と作業効率を支える
- 高圧洗浄や塗料の飛散防止ネットもここに取り付け
- 工事完了後に解体
2階建ての家なら高さ約6m、屋根までしっかりやると7m以上。
見積書の「足場代」が高く見えるのは、安全と品質への“保険料”だと考えてください。
足場架け
家の周りに足場を組み立てる作業そのもの。
塗装の効率アップと安全確保のために必要です。
急勾配の屋根の場合は「屋根足場」も追加されます。
職人がヒョイヒョイ動いているように見えても、実はかなり慎重な世界です。
高圧洗浄
外壁や屋根に溜まったホコリ・コケ・古い塗膜などを
「高圧洗浄機」で一気に洗い落とす作業。
ただ水をかけているように見えて、実はこれが
“塗料の密着度を決める重要工程”です。
古い木造住宅では、水をかけすぎると室内に水が回ることもあるため、
建物の状態を見極めたうえで慎重に行います。
色がのぼる
塗料がしっかり混ざっていないと、
塗膜の表面に軽い顔料が浮き上がり、部分的に色が濃くなってしまう現象。
「同じ色を塗ったはずなのにムラになっている…」というときは、
だいたいこの“色がのぼった”状態です。
しっかり撹拌、大事です。
ウールローラー
芯の筒にモコモコの繊維が付いた、塗装用ローラー。
広い面積をムラなく仕上げるのに向いています。
ハケより技術のハードルが低く、仕上がりもきれいなので
今の塗装現場ではほぼ必須。
ただし、狭いところや細かい部分は今でも“ハケの出番”です。
ウレタン
カルボニル基とアミノ基・アルコール基が手をつないでできた化合物。
と書くと途端に難しくなりますが、要するに
「柔らかくて密着力の高い樹脂をつくる大事な構成メンバー」です。
ウレタン塗料
主成分がウレタン系の塗料。
耐候性・耐水性などバランスが良く、耐久年数は7〜10年程度。
柔らかく密着性が高いので、細かい部分や付帯部に向いています。
“万能型の優等生”というポジションです。
ALC
軽量で断熱性・耐火性に優れた“気泡入りコンクリートパネル”。
外壁・屋根・床など、建物のいろいろな部分に使われます。
工場でパネルとして作り、現場でクレーンなどで吊り上げて取り付け。
性能は高いですが、塗り替え時には専用の知識が必要な素材です。
SOP(エスオーピー)
不透明仕上げの合成樹脂塗料の一種。
オイルペイントの
- 乾燥が遅い
- 光沢が落ちやすい
といった欠点を改善した塗料です。
鉄部や室内木部などに使われます。
エッグシェル
“タマゴの殻くらいのツヤ感”の塗膜状態を指す言葉。
完全ツヤありでもなく、完全ツヤ消しでもない、
ちょうどいい半ツヤのイメージです。
エフロエッセンス(白華)
コンクリートや石材の表面に出てくる白い結晶。
「なんか白いモヤモヤが出てきた…」というあれです。
塗り替え前には、これをきちんと除去しておかないと、
塗料がうまく密着しません。
縁切り
屋根材の重なり部分に溜まった塗料を、
皮スキなどで取り除く作業。
ここが塗料でふさがると、雨水の逃げ場がなくなり
雨漏りの原因になることもあるため、
地味ですが非常に重要な工程です。
化学物質過敏症
空気中にあるごく微量の化学物質に反応し、
体調不良を起こしてしまう状態。
建物が原因となる場合は、
「シックハウス症候群」と呼ばれることもあります。
塗料選びでも“低VOC・水性塗料”などへの配慮が重要になります。
笠木(かさぎ)
塀・手すり壁・パラペットなどの“いちばん上”を覆っている部材。
雨を受け止めるポジションなので、
ここが傷むと中に水が入りやすくなります。
金属・コンクリート・木材など、素材はさまざまです。
金コテ仕上げ
鉄やステンレスのコテで、表面をツルッと平らに仕上げること。
左官職人の“腕の見せどころ”であり、
仕上がりの美しさを左右する技術です。
瓦屋根
U字型の瓦を並べた、昔からある屋根。
瓦にもいろいろな種類があり、
- セメント瓦・モニエル瓦 → 塗装可能
- 和瓦(焼成釉薬瓦) → 基本的に塗装不要・不可
といった違いがあります。
見た目は似ていても、メンテナンス方法は別物です。
環境ホルモン物質
特定の化学物質が、体内で“ホルモンのふり”をしてしまい、
本来のホルモンの働きを邪魔してしまうものの総称。
日常生活の中でも、
建材・塗料・プラスチックなどに含まれている場合があります。
塗料メーカーも、年々こうした影響を減らす方向に開発を進めています。
クラック
外壁に入った「ひび割れ」のこと。
放置すると、そこから雨水が侵入し、内部の劣化や雨漏りにつながります。
細いクラックでも、
将来を考えると“埋めておいたほうが安心”です。
ケレン
塗る前に、鉄部のサビや古い塗膜を削り落として
表面を整える作業。
ここを手を抜くと、
どんな高級塗料を使っても“持ちません”。
派手ではありませんが、塗装の寿命を左右する超重要工程です。
高圧洗浄(※2回目定義)
塗装前の「前処理」としての高圧洗浄。
チョーキング粉・コケ・藻などをしっかり落とし、
塗料が密着しやすい下地をつくります。
下地がデリケートな素材の場合は、水圧を調整して行います。
サイディング
セメント+木質成分などで作られた“工場製の外壁材”。
レンガ調・石調・塗り壁調など、デザインが豊富で、
最近の戸建てでは主流の外壁材です。
継ぎ目にはコーキング(シーリング)が打たれています。
サイディング用クリアー塗料
サイディングの“柄や色”を残したまま、
表面だけを保護する透明の塗料。
「今のデザインは気に入っているけど、
劣化が気になってきた」という時に使われます。
酸化チタン(TiO2)
二酸化チタンとも呼ばれ、
光触媒としても活躍する物質。
ガラスの曇り止めや、汚れが雨で流れ落ちる外壁塗料にも使われます。
“光と仲良しの、きれい好きな物質”です。
シーラー・プライマー
どちらも「下塗り材」の仲間。
- プライマー:金属など“吸い込みの少ない面”に密着を良くする
- シーラー:コンクリートなど“吸い込みの多い面”に使い、吸い込みを抑えたり、弱った下地を固める
名前は違っても、目的は「上塗りを長持ちさせるための土台づくり」です。
下塗り
素地と上塗り塗料を“くっつける”ための最初の塗装工程。
発色を良くしたり、吸い込みを抑えたりする役割もあります。
シーラー・プライマー・フィラーなどがここで活躍します。
シックハウス症候群
建物由来の空気汚染によって起こる体調不良の総称。
ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)や、
カビ・微生物も原因となります。
塗料選びでも「低VOC」「水性塗料」「F☆☆☆☆」といった表記が
非常に重要になります。
遮熱塗料(屋根用・外壁用)
“塗るだけで暑さ対策もできる”近年人気の塗料。
太陽光を反射し、表面温度上昇を抑えることで、
室内温度の上昇も抑え、エアコン負荷を軽減します。
シリコン・フッ素など、既存のグレードに“遮熱機能”を足したイメージです。
シリコン
ケイ素を含む人工の高分子化合物。
安定性・撥水性にすぐれ、汚れがつきにくく、劣化もしにくい。
塗料の世界では“防汚性のエース”的存在です。
シリコン塗料
シリコン樹脂を使った塗料。
耐久年数は10〜15年程度で、今もっともコスパが良い主流塗料。
多くの外壁塗装で“標準仕様”として使われています。
親水性塗料
雨が当たると「水の膜」ができ、
汚れを浮かせて一緒に洗い流してくれる塗料。
ざっくり言うと、
「自分である程度勝手に掃除してくれる外壁」
を目指した考え方です。
水系塗料(水性)
シンナーではなく“水”で薄めるタイプの塗料。
ニオイが少なく、室内や住宅地でも使いやすいのが特徴。
「水性だから弱いのでは?」と思われがちですが、
乾燥後はしっかり塗膜が形成され、水にも強くなります。
スレート屋根
軽くて施工しやすく、価格も比較的おさえられる屋根材。
カラーベスト・コロニアルとも呼ばれます。
近年の住宅でよく採用されていますが、
メンテナンス(塗り替え)は必須です。
退色
外壁の色が少しずつ薄くなっていく現象。
日焼けのようなイメージで、
塗膜の耐候性が弱くなってきたサインでもあります。
タスペーサー
スレート屋根の“縁切り”を、
効率よく・確実に行うための小さな部材。
これを差し込むことで、
屋根材の重なり部分に隙間を確保し、
雨水の逃げ道を作ります。
タッチアップ
塗装の最終チェックで、
細かい塗り残しやムラを修正する“仕上げのひと手間”。
この一手間で、
「まあまあきれいな家」と
「なんかすごくきれいな家」の差が生まれます。
弾性
外壁用塗材の中で、
下地の動きに合わせて“伸び縮み”してくれるタイプ。
ヒビに追従してくれるため、
クラック対策に有効ですが、
弾性が保てるのは5〜7年程度とされます。
チョーキング現象
外壁を触ると、手に白い粉がつく状態。
これが出てきたら“そろそろ塗り替えサイン”です。
放置すると、防水性が落ち、
クラック・微生物汚染などのリスクも高まります。
塗料のグレード
ざっくりとしたグレードは以下の通りです。
アクリル < ウレタン < シリコン < フッ素
右に行くほど耐久年数が長くなります。
ただし費用も上がるため、
「家の寿命」「住む予定年数」とのバランスが大切です。
中塗り
3回塗りの2回目にあたる工程。
上塗りの補強や、膜厚の確保の役割があります。
中塗りをしっかり行うことで、
上塗りの性能がしっかり発揮されます。
刷毛(はけ)
昔からある塗装の基本道具。
今はローラーが主役ですが、
- 端部
- 隙間
- 細かい装飾
など、ローラーが入らないところは
今でも刷毛の出番です。
ハルスハイブリッド塗料
アクリル樹脂をベースに、
ウレタンとシリコンの“いいとこ取り”をした、中間グレードの塗料。
柔軟性+防汚性というバランス型です。
光触媒塗料
光(主に紫外線)が当たることで性能を発揮する特殊塗料。
- 汚れを分解して落ちやすくする
- カビ・藻の繁殖を抑える
- 雨で自動的に洗い流される
など、“セルフクリーニング機能”を持った塗料です。
価格はフッ素クラスですが、メンテナンス性は非常に高いです。
微生物汚染
外壁や屋根に、カビ・藻がついてしまった状態。
見た目が悪いだけでなく、
塗膜機能の低下も意味します。
チョーキングやクラックと合わせて出てきたら、
塗り替えの検討タイミングです。
VOC(揮発性有機化合物)
ペンキ・接着剤・溶剤などに含まれる揮発成分の総称。
独特のニオイの正体でもあります。
過剰に吸い込むと、頭痛・倦怠感・化学物質過敏症などの原因にもなるため、
近年は低VOC・水性塗料が主流になりつつあります。
フィラー
パテ+シーラーの機能を兼ね備えた下塗り材。
小さなヒビを埋めながら、下地を平らに整えます。
モルタル外壁など、クラックが多い外壁では
かなり頼りになる存在です。
吹き付け塗装
スプレーガンで塗料を吹き付ける施工方法。
- ハケ・ローラーでは塗りにくい部分
- シャッター・雨戸など
によく使われます。
ただし、風向き次第でご近所に飛びやすいので、
養生と管理が重要です。
フッ素
非常に反応性の強い元素で、
耐熱性・耐薬品性・すべり性にすぐれた材料(テフロンなど)のもと。
塗料の世界では“超ロングラン選手”をつくるためのキー成分です。
フッ素塗料
主成分がフッ素樹脂の塗料。
耐久年数は15〜20年程度と、現状トップクラス。
その分価格も高いため、
ビル・大型建築・長期保有予定の住宅などで採用されることが多いです。
プライマー・シーラー(再掲まとめ)
どちらも「最初に塗る下塗り材」。
- プライマー:金属などに、塗料の密着を良くする
- シーラー:コンクリートなどに、吸い込みを抑え、弱い下地を固める
名前は違っても、目的は「本番塗装を長持ちさせるための準備」です。
ヘアークラック
髪の毛ほどの細いひび割れ。
「これくらいなら大丈夫でしょ」と放置されがちですが、
水はしっかり入ります。
フィラーなどで埋めればきれいに直ることが多いので、
見つけたら早めの対処がおすすめです。
ホルムアルデヒド
シックハウス症候群の原因物質として有名な有機化合物。
接着剤・塗料などに含まれていることもあります。
現在の建材には、
F☆☆☆☆(フォースター)などの規格があり、
含有量を抑えた製品が使われています。
本塗装(上塗り)
仕上げとなる塗装工程。
一般的な外壁・屋根塗装は
- 下塗り
- 中塗り(本塗装1回目)
- 上塗り(本塗装2回目)
の3回塗りが標準です。
「回数が多ければ良い」ではなく、
“仕様に合った3回をきちんとやる”ことが大切です。
前処理・下地作業・下地調整
塗る前に行う、
- 高圧洗浄
- クラック補修
- ケレン
- 素地に合わせた調整
などの総称。
ここをどれだけ丁寧にやるかで、
仕上がりも耐久性も大きく変わります。
モルタル外壁
砂+セメント+水を混ぜた材料で仕上げた外壁。
継ぎ目が少なく、デザイン性に優れますが、
- 重い
- 施工が難しい
- クラックが入りやすい
といった特徴もあります。
痩せる
塗料が乾燥していく中で、
想定よりも薄く・縮んだ状態になること。
塗膜が薄くなると、
ひびや劣化につながりやすくなります。
溶剤
塗料を薄めて使いやすくするための液体。
塗料用シンナー・ラッカー・水などがこれにあたります。
ニオイ・引火性があるものも多いので、
取り扱いには注意が必要です。
溶剤塗料(油性)
シンナーなどの溶剤で薄めて使う塗料。
- 強溶剤系(ラッカーシンナーなど)
- 弱溶剤系(塗料用シンナーなど)
に分かれます。
耐久性は高いですが、ニオイや室内使用時の換気管理が重要です。
養生
「塗ってはいけない場所」を守るための準備作業。
- 窓
- ベランダ床
- 車・植栽
などをビニールやテープでしっかり覆います。
仕上がりの美しさにも直結する、大切な“下準備”です。