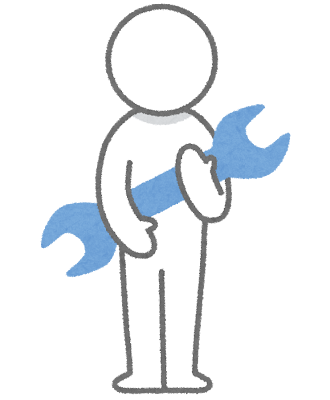今日は少し、いや正直に言えばかなり重たい話です。
でも、こういう話こそ「今、零細企業を経営しているリアル」として、赤裸々にお伝えしたい。そう思って書いています。
■ 22歳の若手スタッフ、退職。
今年、うちの会社で営業管理職として採用した22歳のスタッフが、離職しました。
退職理由は「適応障害」。
もともと彼は、私が通っていたパーソナルジムのトレーナーでした。誠実で、真面目で、コミュニケーションも円滑。正直「この人なら絶対に伸びる」と思い、声をかけて入社してもらいました。
しかし結果として、わずか数ヶ月で心が折れてしまった。
これは完全に、私の経営者としての“教育設計の甘さ”による失敗です。
■ 「即戦力」の幻想と、スタートアップ型経営の難しさ
うちは、大企業ではありません。むしろ、「超」がつくレベルの零細企業。
社員数も限られ、日々のキャッシュフロー(資金繰り)にも細心の注意が必要。
そのため、いわゆる“新人研修”や“長期育成プラン”に時間と予算をかける余裕はありません。
こうした環境下では、どうしても「即戦力性」が求められます。
「トライ・アンド・エラー(試行錯誤)で成長してほしい」
「まずは現場に出て体験を通じて学んでほしい」
そんな思いから、営業管理というポジションにも早めに現場対応を任せました。
ただ、この“実戦投入型”の育成方針は、すべての人に合うわけではありません。
大企業のようにOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)やマニュアルが完備された環境ではなく、周囲も日々現場で手一杯。
リモートでフォローしていたつもりが、実際は彼にとって「誰にも相談できない孤立した状況」になっていたのだと思います。
■ 適応障害の本質とは、環境との“ミスマッチ”
「適応障害」とは、単に心が弱いとか打たれ弱いという話ではありません。
これは環境要因によって心身に不調が現れる状態で、原因となるストレスを取り除けば回復も早いという特徴があります。
つまり、本人の性格や能力よりも、環境との“ミスマッチ”が大きな要因です。
実際、彼はジム時代においては非常に優秀なトレーナーだった。
“自分の強みを活かせるフィールド”では間違いなく輝いていたのです。
では、なぜミスマッチが起きたのか?
それは私の「採用設計」と「職務設計」に問題があったからです。
これは組織論で言うところの「ジョブマッチングの失敗」であり、「適材適所の欠如」です。
■ 零細企業の“人材採用”は、事業戦略そのもの
人をひとり採用すること。
これは、大企業にとっては“数十人の中の一人”かもしれませんが、私たちのような小規模企業にとっては「経営の生命線」です。
一人ひとりが“収益に直結するエンジン”になってもらわないと、経営は回らない。
逆に言えば、一人が戦力化できなければ、他のスタッフへの負担が急増し、全体の生産性が下がってしまう。
この点を私は過小評価していました。
また、私が「怖くない社長」で「話しやすい雰囲気」を出していることで、
「なんとなく雰囲気がいい」「楽そう」と思って入社してくる方もいます。
これはこれで嬉しいことではあるのですが、「入社理由の浅さ」は、定着率に直結する要素でもあります。
■ 「即戦力」ではなく「即・粗利」が必要な現実
本音を言えば、「即戦力」では足りないんです。
うちのような会社に必要なのは「即・粗利(グロスマージン)」を生み出せる人材。
塗装業界では、受注額のうちどれだけが粗利として残るかが極めて重要です。
利益が出なければ、給料も払えないし、次の採用もできない。
例えば「現場管理ができる」「見積もりができる」「商談ができる」人材なら、年収600万円スタートでも構わないと思っています。
問題は、「そこまでいける人材」をどう育てるか。
または、最初からそういう素養を持った人をどう見抜くか。
この“目利き”と“設計力”が、経営者としての腕の見せどころだと痛感しています。
■ 「教育か、即戦力か」の葛藤
人を育てるには時間と労力と“資金”が必要です。
でも、すぐに結果を求めれば、育つ前に辞めていく。
このジレンマのなかで、私は「育成スピードと離職リスクのバランス」を見誤ってしまいました。
やはり、採用段階で「この会社がどういう環境なのか」「何が求められるのか」「何が得られるのか」をもっと正直に、具体的に伝えるべきでした。
そして、「育てる覚悟」と「待つ余裕」を持たないといけない。
この“余裕”を作るのは、結局のところ「安定した利益」です。
■ これからのモナツキの採用方針
今後は、以下のようなスタンスで採用を見直します。
- 成長意欲より“行動力重視”
- できることより“結果を出せる環境を選ぶ力”重視
- 気軽さではなく“厳しさの中のやりがい”を伝える
その上で、「数字で評価されたい人」「自分の成果をしっかり報酬に変えたい人」にこそ、うちの会社を選んでほしいと思っています。
■ 最後に:お客様へ
こうした採用の失敗も、最終的には「お客様満足度」に直結します。
ですから私自身、改めて“内部の体制強化”にも取り組んでまいります。
そして、見守ってくださっているお客様、支えてくれているスタッフ、すべての関係者の皆様に感謝しながら、これからも現場第一・品質第一で走り続けます。
まだまだ未熟な会社ですが、少しずつ、確実に前へ進んでいきます。
以上、長文となりましたが、読んでいただきありがとうございました。
この「ぶっちゃけブログ」が、今後の採用や経営に悩む他の小規模事業者の方にも、何かヒントになればうれしいです。